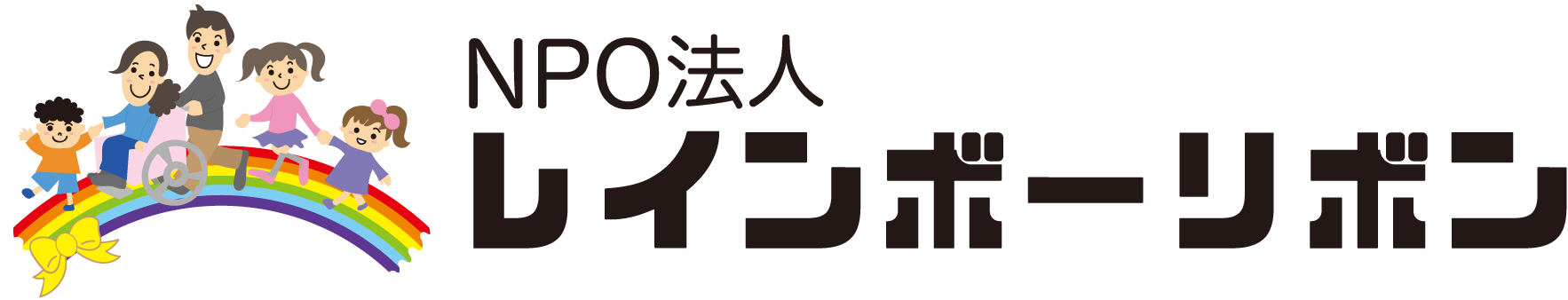レインボーリボン メールマガジン 第135号 子どもの声からはじめよう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ レインボーリボン メールマガジン 第135号
■■ 子どもの声からはじめよう
2025/6/30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東京都葛飾区を拠点とするNPO法人レインボーリボンの活動報告、代表の緒方の思いをお伝えするメールマガジンを毎月、月末にお届けしています。
年間、数校からのご依頼がある「いじめ防止教室」ですが、この6月、初めてご依頼があった2校で実施させていただきました。
埼玉県と神奈川県、両校とも県境を越えての移動で、方向感覚も地理感覚もない私としては、4週にわたって2校で5日間、全10時間の授業は、まずは遅れずに学校にたどり着くことが必須の課題でした。
授業の準備にも緊張感をもって取り組みました。
かれこれ10年も取り組んでいますとお話したところ、校長先生から「このプログラムを完成させるにはどのくらいかかったのですか?」と聞かれましたが、いまだに完成はしていないのです。
ご依頼をいただくとほぼ毎回、授業案を見直し、新たな知見や考え方、時代とともに進んでいる「子どもの権利」擁護の手法を取り入れるようにしています。
今回は内容に大きな変更は加えませんでしたが、子どもたちの前で話をさせていただく「自分」の態度やペース、強弱のつけ方を強く意識しました。
この1カ月間、一般社団法人「子どもの声からはじめよう」の「子どもアドボカシー講座 基礎」を受講していたことが大きく影響しています。
https://www.kodomonokoekara.or.jp/
この講座は毎週末、全8回の講座参加とそれぞれの回での事前動画視聴、事前レポート提出、講座受講後のレポート、終了後の修了レポートの提出が必須で、時間的体力的に非常にキツかった…。
しかし、この講座を受講中だったために、いじめ防止教室で出会う子どもたち一人ひとりの声を聴き洩らさないように、子どもには声をあげる権利があるのだと知ってもらえるように、実際に声をあげる力をエンパワメント(※1)できるように…と、授業の目的を意識することができました。
※1 エンパワメントとは、力を与えることや自信をつけさせること。自己決定や自己実現を促すこと。
子どもの声を聴く「子どもアドボカシー(※2)」、子どもの声を大きくし、伝えたい人に伝えるマイクの役割を担う「子どもアドボケイト」は欧州やカナダで発展した考え方、制度で、1981年にはノルウェーで「子どもオンブズパーソン」が公的な機関として設置されました。
※2 アドボカシーとは、「アドボケイト」と同じ語源で「擁護・代弁」や「支持・表明」「唱道」などの意味。
日本では2022年の児童福祉法改正により、①児童相談所や児童福祉施設における意見聴取等措置、②意見表明等支援事業(独立アドボカシー)、③こどもの権利擁護に係る環境整備――が規定されたそうです。
① は児童相談所に一時保護されたり、児童養護施設で暮らしている子どもの意見を聴くよう、意見箱を設置したり、第3者評価を実施するという内容です。
② は上記のような社会的養護の下にいる子どもたち対象に、行政や施設から独立しているアドボケイトが訪問し、意見表明を支援するための事業です。
③ は各自治体に設置される児童福祉審議会が子どもの権利救済の役割を担う案が検討されていますが、全国レベルではまだほとんど機能していないようです。
私が受講した基礎講座では、①の受け入れ側の子ども支援者がアドボカシーの理念を学び、日々の福祉活動として実装している姿や、②の訪問アドボケイトの活動に触れることができました。
「アドボカシーはケアとはちがい、目の前の子どもからもらった情報のみを受け取る」
「アドボケイトは『子どもの最善の利益』は考慮せず、ただ、子どもの声を聴く」といった、やや哲学的な講義に、最初はなかなか納得がいかず、「そうは言っても、こども食堂では『子どもの最善の利益』を目指して様々な情報を収集したり、親と子どもの利益が相反するときには行政や専門家に相談しながら少しでも親子の幸せに近づけるように話をしたり、行動している」という自負もあり、今まで素人なりに「子どもソーシャルワーク」を志し、環境を変えるために頑張ってきたことを否定しなければならないのかな…と、悩みました。
しかし、最終回の第8回講座を受けてようやく腑に落ちました。
子どもが発する言葉は氷山の一角であり、氷山の水面下に隠れた様々な要素を汲み取り、見える化するためには、子どもが安心して話ができると感じられる信頼関係と、大人も自分自身の権利が守られていて子どもの声を受けとめることができる状態、そして環境的なタイミングを得なければ、子どもとの共同作業としての「意見表明」に取り組むことはできないのだと。
いじめ防止教室の外部講師として出かける身では、信頼関係の構築はとても無理だと感じます。
でも、子どもの声を受けとめてくれる大人を諦めずに探してね、スクールカウンセラーさんは守秘義務があるから、親や先生に知られたくない気持ちは守ってもらえるよ…と訴えました。
被害者、加害者、傍観者のそれぞれの立場で「行動を変えよう」と呼びかけた授業を終えて、アンケートに「自分が相談できるところをみつけて、自分の心を守っていこうと思いました」と書いてくれた子がいます。
施設への訪問アドボケイト等、レインボーリボンとして新しい活動を始めることは今はできませんが、こども食堂、いじめ防止教室、PTA研修など、継続している活動の中で、「子ども・若者の声からはじめよう」というスタンスを大切にし、「大人」としてではなく、「自分」として関わること、自分の中の多様性・グラデーションを理解・受容することが人への理解・受容につながるという「生き方としてのアドボカシー」を意識していきたいと思います。
(代表・緒方美穂子)
▼レインボーリボンのメールマガジン、バックナンバーは下記URLでご覧いただけます。
http://rainbow-ribbon-net.org/category/mailmagazine/
▼レインボーリボンの活動を支えるご寄付をお願いいたします。
●寄付サイト「誰も取り残さない、多文化共生の子ども支援」
https://congrant.com/project_iframe/rainbow-ribbon/17787
●寄付サイト「誰も取り残さない地域社会をつくるこども食堂とフードパントリー」
https://giveone.net/supporter/project_display.html?project_id=20483
●銀行口座:りそな銀行 青戸支店(店番号470)普通預金1520535 特定非営利活動法人レインボーリボン
●郵便振替口座:00170-7-449974