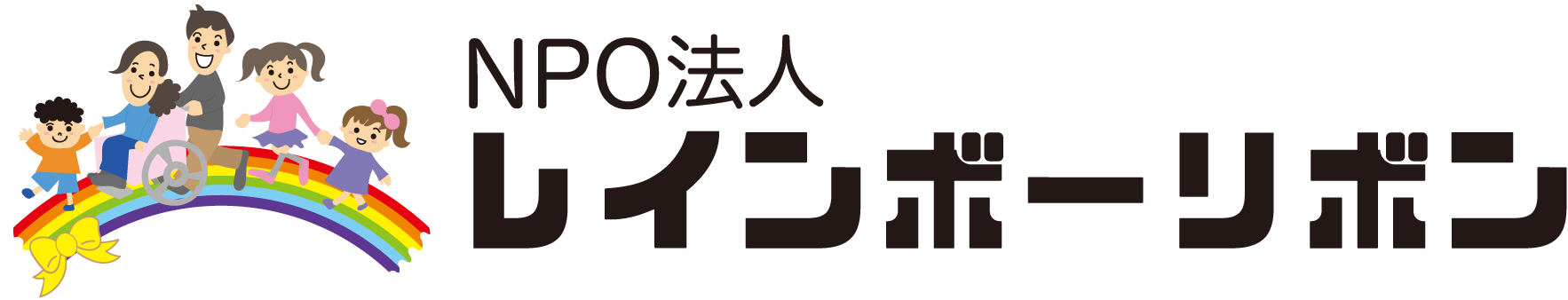レインボーリボン メールマガジン 第137号 「オープンダイアローグ」をやってみたい
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ レインボーリボン メールマガジン 第137号
■■ 「オープンダイアローグ」をやってみたい
2025/8/31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東京都葛飾区を拠点とするNPO法人レインボーリボンの活動報告、代表の緒方の思いをお伝えするメールマガジンを毎月、月末にお届けしています。
戦後80年の8月、連日35度を超える猛暑の東京で、テレビから流れる広島平和記念式典のこども代表「平和への誓い」を聞きました。
「どんなに時が流れても、あの悲劇を風化させず、記録として被爆者の声を次の世代へ語り継いでいく使命が、私たちにはあります。
世界では、今もどこかで戦争が起きています。
大切な人を失い、生きることに絶望している人々がたくさんいます。
その事実を自分のこととして考え、平和について関心をもつこと。
多様性を認め、相手のことを理解しようとすること。
一人一人が相手の考えに寄り添い、思いやりの心で話し合うことができれば、傷つき、悲しい思いをする人がいなくなるはずです」
過去から未来へと続く時の流れの中で、「今」を生きる私たちの使命。
過去の侵略、植民地支配、民族差別の歴史を背負いながら、今、そして未来に向かって、平和に平等に、仲良く共に生きていこうと願っている東アジアの、日本という国、そこから見ている世界。
「Think Globally, Act Locally(地球規模で考え、足元から行動を)」は、地球環境保護を訴えるスローガンですが、私にとっては、この暑さに苦しむ身体の中から聞こえる内なる声でもあり、また、本当に核のボタンを押しかねない世界の国家リーダーたちに向けた、子どもたちの悲痛な叫びにも聞こえます。
「一人一人が相手の考えに寄り添い、思いやりの心で話し合うことができれば、傷つき、悲しい思いをする人がいなくなるはずです」。
このことをずっと考えています。
レインボーリボンが発足当初から取り組んでいる「いじめ防止教室」についてです。
いじめ防止教室では「行動を変えよう」という呼びかけをしていて、被害者は「逃げる」、加害者は「加害をやめる」、傍観者は「いじめをなくすために自分にできる行動を」と推奨しているのですが、何と言っても一番の肝は、加害者が「加害をやめること」に決まっています。
しかし、これが一番、難しいことです。
いじめ防止教室の加害者理解の授業では、子どもたちに「いじめっ子ってどんな子?」「なぜ、いじめをするの?」と考えてもらいます。
単純な動機であれば、先生に指導してもらうとか、また、いじめ防止に意識的に取り組めば、具体的に改善される行動があると思います。しかし、いじめっ子自身にいじめ被害体験があったり、あるいは、家庭で虐待を受けている…といった場合は、加害行為の源泉に「心の傷」が想定されます。加害者がその「心の傷」を克服しなければ、つまり加害者の「被害者性」に焦点をあてなければ、加害行為を根源的になくすことはできないでしょう。
これはPTSD治療とか、養育環境を改善するソーシャルワークとか、とても素人には手に負えない領域のような気がします。
でも、本気でいじめをなくしたいのなら、この問題を避けては通れない…。
『いじめ加害者にどう対応するか』(岩波ブックレットNo1065)を読んでいて、ひきこもり支援で有名な精神科医の斎藤環先生が紹介している「オープンダイアローグ」という方法に興味をもち、『オープンダイアローグとは何か』(医学書院 斎藤環著・訳)と、『まんが やってみたくなるオープンダイアローグ』(医学書院 解説・斎藤環 まんが・水谷緑)の2冊を購入しました。
専門書に取りかかる前に、まんが解説書の方から先に読みました。
オープンダイアローグ(開かれた対話)とは、最重度の統合失調症を含む多様な精神病を対象として、家族療法、精神療法、グループセラピー、ケースワークといった多領域にわたる知見や奥義を統合したような治療法だそうです。
しかし、その手法は極めてシンプルです。
オープンダイアローグ発祥の地、フィンランドのケロプダス病院では、患者かその家族から依頼があれば、24時間以内に初回のミーティングが開かれるそうです。参加者は患者本人とその家族、親戚、本人に関わる重要な人物。治療者は医師、看護師、心理士等、数名から成る専門家チームです。
1時間半程度のミーティングは危機が解消されるまで毎日でも続けられ、薬物治療や入院の是非などの決定は、本人を含む全員が出席してなされます。
ミーティングの途中で専門家のみの「リフレクティング」という時間があり、患者や家族の目の前で治療者が感想、見解を出し合います。
まんがを読んで「なるほど~」と思ったのが、治療チームも多様な人間で、それぞれがちがった意見を患者に差し出すのです。患者本人が差し出された多様な意見を吟味して、自分の中で消化し、応答していくので、自分の矛盾や不整合に自発的に気づき、結果的に正常化が起こるということです。
だから、薬や電気ショックで治療を受けた患者は自分が「治った」とはなかなか納得できないのに、オープンダイアローグでは患者が自発的に「治った」状態に至り、医者が「いったい何が良かったんだろう」と、ポカンとするのだといいます。
当事者の見ている世界、体験している出来事を、チームで真摯に傾聴し、批判や決めつけをせずに関心を持ち続け、正解や「合意」を目指すのではなく、ひたすら対話をつづける。その対話の「副産物」として、当事者に「正常化」が起きる。
この手法は「いじめ」の加害者が行動を変えるために応用できるのでは?
「一人一人が相手の考えに寄り添い、思いやりの心で話し合うことができれば…」。
戦争をなくすためにも役に立つのでは?
民族の歴史、被害感情を利用している政治家は別として、民衆同士の対話であれば、パレスチナ人とイスラエル人、ウクライナ人とロシア人、それぞれの物語をひたすら聞き、意見し合い、握手できなくても対話をつづける、そんなオープンダイアローグの舞台を、歴史的地理的な利害関係があまりない国の仲介チームがお膳立てできないものだろうか…。
夢は広がる…。ですが、専門書の方をわからないなりに読み進むと、やはりそんなに簡単ではないな…とも思いました。
そもそも岩波ブックレットで斎藤先生は「わたしには今の学校に加害者支援のような『高級』なことができるとはとても思えません。その前に、まずは被害者支援を十分にやることを優先するべきです」と言っています。
それでも、例えば加害者が「出席停止」という処罰を受けたら、その間、学校の外で私たちNPOのような第3者が専門チームとなって、加害者とその家族と、オープンダイアローグに取り組むことはできないだろうか。
まあ、それこそ、かなり先の「夢」としても、斎藤環先生の講演会開催をまずは目指そうかな…。
(代表・緒方美穂子)
▼レインボーリボンのメールマガジン、バックナンバーは下記URLでご覧いただけます。
http://rainbow-ribbon-net.org/category/mailmagazine/
▼レインボーリボンの活動を支えるご寄付をお願いいたします。
●寄付サイト「誰も取り残さない、多文化共生の子ども支援」
https://congrant.com/project/rainbow-ribbon/17787
●寄付サイト「誰も取り残さない地域社会をつくるこども食堂とフードパントリー」
https://giveone.net/supporter/project_display.html?project_id=20483
●銀行口座:りそな銀行 青戸支店(店番号470)普通預金1520535 特定非営利活動法人レインボーリボン
●郵便振替口座:00170-7-449974