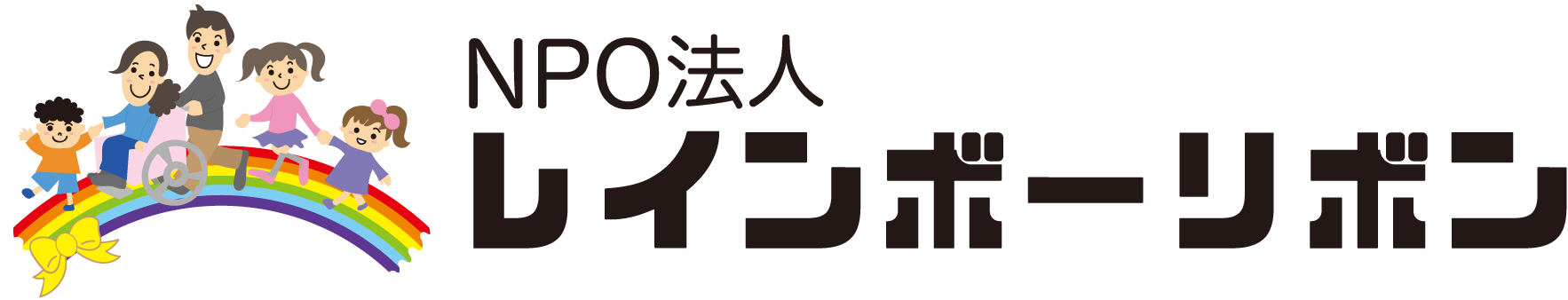レインボーリボン メールマガジン 第131号 私たちは「かかりつけ医」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ レインボーリボン メールマガジン 第131号
■■ 私たちは「かかりつけ医」
2025/2/28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東京都葛飾区を拠点とするNPO法人レインボーリボンの活動報告、代表の緒方の思いをお伝えするメールマガジンを毎月、月末にお届けしています。
2月は毎週土曜日のこども食堂・フードパントリーに加えて、準備に何カ月もかけてきたような大型の企画や会議が何件もあり、たいへんな月でした。
レインボーリボンの活動は法人化前のPTA時代も含めるともう20年近くなります。
私は若い頃は取材して記事を書く仕事をしていたのですが、大好きだったその仕事も、数えてみれば10年ほどのキャリアしかありません。
それなのに、レインボーリボンの活動はよく続いているなあと、我ながら感心します。
その中でも、今月は「初めての挑戦」が2件もありました。
「いじめ防止教室」は10年前の法人化とほぼ同時に取り組み始めた活動ですが、心理カウンセラーの先生が実施している「いじめ防止プログラム」の現場に何度も足を運び、葛飾区で実践するために自分なりに工夫を重ねて作ってきたプログラムです。
小学5年生から中学1年生くらいの、1クラスごとに4時間かけて実施する内容です。
この取り組みを高く評価してくださっている地元の校長先生の依頼で、今年はなんと、1年生から6年生までの全校児童を対象とし、1時間の道徳公開授業を行いました。
https://rainbow-ribbon-net.org/blog/20250208ijime/
1年生にも理解できるように、6年生が退屈しないように、前日の深夜まで講義内容を練った甲斐があり、真剣な眼差しで話を聞いてくれる子どもたちに、こちらが勇気づけられました。
この経験が生きたのが、今月2件目の「初めての挑戦」、女子柔道大会での講話です。
https://rainbow-ribbon-net.org/kodomosyokudou/20250216judo/
柔道のことは何も知らない私が、レインボーリボンの活動の中で出会ってきた子どもたちの話をしたのですが、小学1年生も中学生も、大会運営側の先生方もとても熱心に聞いてくださいました。
子どもたちは、このメルマガの前号で紹介した「Fちゃんのはたちのお祝い」の写真が見たいと、自然に前に出てきてくれました。
女子柔道大会で「レインボー」が象徴する「性の多様性」について、「『性』という漢字はりっしんべんに生きると書きます。りっしんべんは『心』という意味。『性』は心が生きている状態です。心は自分だけのもの。誰かに決められるものじゃないよね?」と話しました。
これは実は、今月初め、地元の青少年育成地区委員会で企画した性教育の講座で講師をお願いした認定NPO法人ピッコラーレの内田優子先生のお話が元ネタです。
アメリカのトランプ大統領の「『性』は男性と女性の2つ」「トランスジェンダーのオリンピック参加は認めない」といった発言を聞いて、その「決めつけ」と「排除」によって傷つく子どもたち、大人たちを慰め、共に生きていく連帯の言葉として最適だなと思ってパクらせていただきました。
「レインボー」は7色の個性、多文化、多様性を表しています。
「リボン」は私たちが横につながっていく連帯の絆、子どもたちの未来につなげていく持続可能性を表現しています。
「みんなちがってみんないい」多文化共生の価値観を、いま、隣にいる横の人間関係にも、時間軸を縦に、未来の人間社会にも結んでいきたいという願いを込めた団体名です。
団体の原点であり、活動継続の原動力となっているこの理念に改めて立ち返ることができたのは、この2年間、葛飾区の社会教育委員という任務を拝命し、「区民の誰もが生涯にわたって学び続けるしくみづくり――“学びによる循環型社会”の構築――」というテーマを考えてきたからです。
2月4日、第14期葛飾区社会教育委員の会議として、生涯学習課のもとで協議してきた「提言」を教育委員会に提出しました。
社会教育委員の今期の会議は、議長に早稲田大学の髙井正先生、副議長に駒澤大学の萩原建次郎先生を招き、区内の生涯学習に関わる関係者や小中学校の校長先生をメンバーとして、一昨年の6月からほぼ毎月、17回の会議を重ねてきました。
髙井議長は「こういう文書は行政の事務局が書いてしまうことが多いのですが、この提言は本当に自分たちで書くんだと、途中で気がつきました」と苦笑していましたが、本当に「“学びによる循環型社会”って何だろう」「どうしたら作れるのだろう」と、メンバーみんなで意見を出し合い、他の自治体に視察に出かけたり、学生時代に戻ったような楽しい、苦労も多い(提言執筆のご苦労はほとんど議長、副議長に任せきりでしたが)2年間でした。
提言では、学びには「縦の循環」と「横の循環」があると定義し、「縦の循環」としては①個人内での学びの深まりと継続の循環、②多世代が共に学び育ち、世代継承と持続可能な地域コミュニティづくりへ連なる循環――の2つの側面があるとしました。
「横の循環」としては、①学びを基盤とした活動同士がつながり、学びと活動の輪が広がる循環、②学習機会への参加から学習をつくる参画への循環――の2つの側面があると指摘しています。
まさにレインボーリボンがたどってきた20年を振り返るような議論をさせていただきました。
PTA活動での気づきから出発し、学びと活動の循環を繰り返しながら今日も楽しく継続しています。
区のHPにはまだ前期の提言までしか掲載されていませんが、近日中に私たちの提言も公開されると思いますので、お読みいただければ幸いです。
https://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000084/1006015/1030257/index.html
今月は「かつしか子ども食堂・居場所づくりネットワーク」に属する団体と、葛飾区の福祉や子育て支援関連の行政担当者との合同勉強会も実施しました。
https://katsushika-kodomoshokudou.net/2025/02/19/jireikenntou/
まったくのシロウトである地域住民が、こども食堂で困難を抱える子どもに出会ったらどうしたら良いの?というテーマで、グループワークを通して「このような場合はこの窓口に」といったケース検討を行います。
私のグループでは「虐待を受けているかもしれない」というケースを話し合いました。
まずは子ども家庭支援課(葛飾区では「子ども総合センター」、一般的には「子ども家庭支援センター」=子家セン(コカセン))に相談。重篤な虐待ケースは児童相談所(児相)が対応する――といった手順を学んだボランティアの参加者が「児相は大病院、子家センはクリニックのようなものですね」とまとめました。
すると、グループにいた児相職員と福祉部署の職員さんが「皆さんは『かかりつけ医』ですね」と返してくれました。
まったくのシロウトだけど、「かかりつけ医」。
子どもたちの近くにいて、信頼されていて、つらいことでも打ち明けてもらえる、そしてクリニックや大病院への紹介状を書くような適切な対応ができる――。本当にそんな誇り高いボランティアに、私たちは成長し続けていきたいものです。
(代表・緒方美穂子)
▼かつしか区民大学「葛飾の子ども・若者はいま――不登校34万人時代のリアル」
レインボーリボン代表の緒方が現役中学生に「学校のリアル」についてインタビュー。
葛飾区教育委員会・元中学校校長の目々澤幸雄先生に「校内サポートルーム」の実践と公教育のあるべき姿を聞きます。
グループで話し合い、子ども・若者が安心と自信をもって成長できる未来を描きましょう。
日時: 3月16日(日)午後2時~4時30分
場所:亀有地区センター
対象:どなたでも(15歳未満は保護者同伴)
参加費:無料
申込(3月5日締切):https://logoform.jp/form/Ehiz/834717
▼レインボーリボンのメールマガジン、バックナンバーは下記URLでご覧いただけます。
http://rainbow-ribbon-net.org/category/mailmagazine/
▼レインボーリボンの活動を支えるご寄付をお願いいたします。
口座名義:特定非営利活動法人レインボーリボン
●郵便振替口座:00170-7-449974
●りそな銀行 青戸支店(店番号470)普通預金1520535
●寄付サイトGiveOne こども食堂・フードパントリープロジェクト
https://giveone.net/supporter/project_display.html?project_id=20483