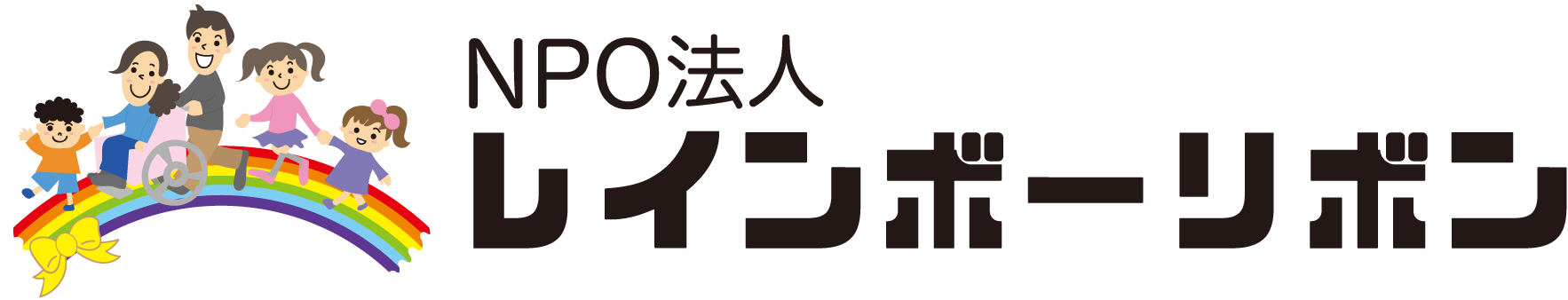レインボーリボン メールマガジン 第132号 「いやだった」と言えて初めて、旅立てる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ レインボーリボン メールマガジン 第132号
■■ 「いやだった」と言えて初めて、旅立てる
2025/3/31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東京都葛飾区を拠点とするNPO法人レインボーリボンの活動報告、代表の緒方の思いをお伝えするメールマガジンを毎月、月末にお届けしています。
卒業、旅立ちの季節です。
3月半ばの日曜日、中学校の卒業式を数日後に控えた15才のKくんに、義務教育の9年間を振り返ってもらうインタビューをしました。
地元の地区センターで開催された、かつしか区民大学「葛飾の子ども・若者はいま――不登校34万人時代のリアル」講座の壇上です。
Kくんとの出会いは3年前。今回と同じ、かつしか子ども・若者応援ネットワークが企画した子どもの権利に関する講座に、お母さんと一緒に参加してくれたのでした。
当時は中学校の理不尽な校則や謎ルール、生徒の主体的行動を制限する指導に対する不満、怒りを吐露してくれたKくんでしたが、今回のインタビューでは、意外にも中学校は「楽しかった」と。
校則などの理不尽さはまだ払拭されていないけれど、授業は一方通行ではなく、ほぼ必ずグループワークが組み込まれ、高校受験は「チーム戦だ!」と号令をかけられ、仲間と協力して勉強に取り組んだそうです。
「個別最適な学び」「主体的な学び」「協働的な学び」を謳った学習指導要領(2022年完全実施)に沿って、学校は変わりつつあるようです。
大勢の聴衆の前でも落ち着いてしっかりと自分の考えを伝えることができるKくんですが、小学4年生頃から中学1年生にかけて、たびたび不登校を経験しています。
あることがストレスとなり、起立性調節障害となってしまったそうです。
しかし、小中9年間を通して全体としては「楽しかった」「成長できた」と堂々と語ることができているのはなぜでしょうか。
その答えは、Kくんが「子どもの権利」を知っていたからです。
小学生のときに、あるワークショップに参加して、子どもには安心安全に生きる権利、教育を受ける権利、成長する権利、自分の気持ち(意見)を表明する権利などがあることを知っていました。
不登校になったとき、スクールカウンセラーに自分の気持ちを話すことができたそうです。
親御さんもKくんの気持ちを尊重して、休ませてくれたそうです。
不登校の子どもが心を休ませて、人への信頼を失うことなく、また「学び」に向かっていく意欲を回復するためには、「子どもの気持ち(意見)」を受けとめる、尊重する、ということがどんなに大切か、続いて講演していただいた元中学校校長の目々澤幸雄先生の「校内サポートルーム」の実践からもよく分かりました。
文科省の「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」(2023年)の7年も前から、教室に入れない子が別室登校できるような「居場所」(現在の「校内サポートルーム」の前身)を開設していた葛飾区の中川中学校で、目々澤先生は子どもたちに寄り添ってきました。
先生は、不登校を選択したばかりの子どもたちは、とにかく「こころの自信」を取り戻すまで大人と一緒に休養することが必要だと言います。サポートルームでは休み、お喋りをし、ゲームをし、心が回復したら子どもは自分から「教室に行ってみようかな」「授業を受けてみようかな」と言うそうです。
講演の最後に、クイズがありました。
「長い時間をかけてようやく教室に入って、授業を受けて、サポートルームに帰ってきた子が最初に言うひとこと、感想は何でしょうか?」
答えは「いやだった」、だそうです。
なるほど、それはそうですよね。「いやだった」という気持ちを言えて、良かったですね。
その子はもう大丈夫ですね。
「いやだった」という気持ちを伝えることができる大人が周囲にいないまま、卒業年齢を迎える子が一番心配です。
ヤングケアラーであったり、ネグレクト家庭であったり、過酷な成育環境を背負って自分の気持ちは固く閉じ込めて、その日その日をやり過ごして来た子は、「さあ、旅立ちなさい」「自立しなさい」と言われても、飛び立つ方法も知らないし、羽ばたくパワーを蓄えることもできていません。
私たちが地域でこども食堂などの活動を続ける究極の目的は、家庭や学校で困難を抱えている子どもをできるだけ早く発見し、安心できる「居場所」や適切な支援につなげることです。
私たち自身が安心できる「居場所」となれるように、一緒に遊んだり学んだりしながら、子どものありのままを受けとめられる大人になろうと、努力しています。
でも、民間の我々のボランティア活動だけでは、子どもたちの困難な状況を変えることは不可能です。そこで、行政に期待するわけですが…。
区民大学講座の翌日には「第7回子育て支援団体と子ども未来プラザの連携に向けた意見交換会」がありました。
葛飾区が「地域における子どもの育ちを支援する環境づくりの拠点」として整備を進めている「子ども未来プラザ」と、我々、子ども・子育て支援団体のネットワークとの意見交換会です。
「配慮を必要とする子どもと家庭への支援の充実」など、区が定めたガイドラインを実装するための具体的な協働のスタイルがなかなか見えてこない会議で、いつも消化不良の感が否めません。
「こどもまんなか」の議論じゃないからだよな…と、いつも思います。
未来プラザを利用する子ども、こども食堂に来る子ども、どちらにも来ない・来られない子ども、一人ひとりの気持ちと権利に関係のないところで、行政と民間が意見交換をした、という形だけの会議になっている気がします。
形だけ、マンネリ、アリバイに陥っていないか。
私たち自身の活動にも自省が必要です。
13年前に「こども食堂」というネーミングの産みの親となった大田区「だんだん」の近藤博子さんが先日、「『こども食堂』の大きな流れからは、一線を引こうと思います。やめるわけではなく、『だんだんの想い』を大切にしていくために、『こども食堂』という名前を宝箱にしまおうと思います」とSNSに投稿しました。
「こども食堂」という看板は便利です。
ACジャパンのコマーシャルのような明るいイメージがあり、善意の象徴のように扱われ、子どもの幸せを実現できているかのような、「成果」が見えやすい活動です。
この便利な看板にすがって、「私たちは良いことをしています。寄付してください。誰でも来てください」と安易な活動に陥ってしまったら、私たちは、困難を抱えた子どもたちには決して寄り添えないでしょう。
政治・行政はどうでしょうか。こども食堂に助成金を出していれば、それで「子どもの貧困」は解決されるのでしょうか。
4月からの新年度、子どもの気持ちをまんなかに、マンネリ、アリバイに陥らないように気をつけながら、私たちの活動の在り方を考え続けたいと思います。
(代表・緒方美穂子)
▼レインボーリボンのメールマガジン、バックナンバーは下記URLでご覧いただけます。
http://rainbow-ribbon-net.org/category/mailmagazine/
▼レインボーリボンの活動を支えるご寄付をお願いいたします。
口座名義:特定非営利活動法人レインボーリボン
●郵便振替口座:00170-7-449974
●りそな銀行 青戸支店(店番号470)普通預金1520535
●寄付サイトGiveOne こども食堂・フードパントリープロジェクト
https://giveone.net/supporter/project_display.html?project_id=20483